

こんにちは、広報課です。
2022年4月1日より、妊娠・出産の申出をした従業員に対して、育児休業等の制度周知と育児休業の取得意向確認が義務付けられたほか、2022年10月からは原則分割ができなかった育休を2回に分けて取得することが可能となり、男性の育休については「産後パパ育休」という制度が新設されました。
育児休業を取り巻く環境が変化するなか、2023年度の西鉄の男性育休取得率は、社内目標である30%以上を大きく上回る54.4%となりました。
今回は、今年4月より1年間の育児休業を取得中の都市開発事業本部 企画開発部 村上弘晃さんにお話を伺いました。
今回お話くださる方
 村上 弘晃 さん
村上 弘晃 さん
2012年入社 都市開発事業本部 ビル営業部 営業課
(費用担当→収入担当→管理担当)
2017年 都市開発事業本部 企画開発部 建築技術担当
(社用施設担当→統括担当→SC施設担当)
家族構成:妻(専業主婦)、長男(2歳)、次男(0歳6か月)の4人家族です。
育休取得のきっかけは?
男性も育休が取得できるという制度自体は知っていましたが、お世話になっている先輩(清海さん)が1年間取得されたことで、具体的に考えるきっかけをいただきました。また、長男の時は子どもと接する時間が思うように取れなかったことを残念に思っており、次があれば取得したいと考えていました。
育休を取ると告げたときの周りの反応
会社では最初に、直属の上司である課長に相談しました。突然の相談だったにも関わらず前向きなコメントをいただき、「後輩たちのモデルケースになって欲しい」と言っていただきました。非常に嬉しかったです。身内に相談した際、妻は私の考えに賛同してくれました。両親にも話す機会があったのですが、給与面や今後の会社での待遇面等は心配されました。ただ、家族との時間を優先したいという私の気持ちには理解を示してくれ、反対はされませんでした。
取得に際し、不安だったこと、わからなかったこと、困ったこと
会社への手続き等は人事サービスの方にサポートしていただき、問題なく進めることができました。育休取得中の給与面は少し不安でしたが、育児休業給付金の制度が私の気持ちを後押ししてくれました。また、次男の誕生が3月中旬で、新年度が始まる4/1から育休を取得したため、通常の人事異動にあわせて業務の引き継ぎができたことはラッキーでした。
現在どのような一日を過ごされていますか。一日のスケジュールや家事の分担などありましたら教えてください。
私が料理と子どもたちの入浴、妻が洗濯と掃除、というような分担にしつつ、日によって臨機応変にしています。私はこれまで料理の経験が無かったのですが、育休を機に挑戦中です。また、妻が専業主婦ということもあり、長男は保育園や幼稚園に入れていなかったので、基本的には私が長男担当、妻が次男担当という形をとっています。長男はイヤイヤ期と赤ちゃん返り、次男は夜泣きでなかなか眠れない日が続いて大変ですが、妻と2人で分担して見ることができ、大変ながらも楽しんで子育てができていると感じます。
育休取得前はもう少し余裕のある生活をイメージしていたのですが、実際は子どもたちと格闘しているうちに一日が終わってしまいます。朝起きたら朝食を作り、食事が終わったら買い物に出掛けたり、公民館等でのイベントに参加してみたり。お昼前には昼食を作り、食事が終われば子どもの寝かし付け。無事に寝てくれた後は夕食の準備をし、子どもが起きたらお風呂に入れます。夕食が終われば、少し子どもと遊んでから一緒に寝ます。頭の中ではいつも料理のメニューや作る手順、どのお皿に盛りつけるか等を考えていて、仕事のときよりも頭を使っているかもしれません。
育休をとってみて感じること
昨年、長男と2人で寝ようとして大泣きで拒絶されたことがありました。それが今では、長男のほうから「パパと寝たい!」と言ってくれます。家族で過ごす時間が増えたことで、子どもたちとの距離がぐっと近くなりました。子どもたちは少しずつ話せる言葉が増えたり、できることが多くなったりして、日々成長する姿を見ていると楽しく、「もっと頑張ろう」と活力が湧いてきます。
今後は男性・女性関係なく、育休を取得する方・したい方が増えていくと思いますので、私自身は取得したい方のサポートができれば嬉しいです。また、実際に育休を取得した私だからこそ、育休取得前・取得中の悩みや困りごと等の相談にも乗れると思っています。職場復帰後はこの経験を生かして、後輩たちが働きやすい職場をつくっていきたいです。
村上さん、どうもありがとうございました!!
それぞれのワーク・ライフ・バランス。何かを考える、行動する一助となれば幸いです。
★以下人事より関連情報のお知らせ★
2024年度の目標は、配偶者出産休暇制度が新設されたこともあり、育児休業と配偶者出産休暇(有給)を合わせて90%以上としています。各種制度を活用し、育児に参加することで家庭と仕事の両立を目指しましょう!

その他の情報はイントラネットよりご確認ください→シゴトと子育て・介護の両立ハンドブック (nnr.co.jp)







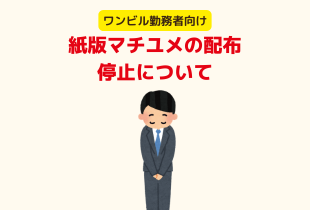








この記事へのコメントはありません。