

前回の記事は飲酒運転によって、加害者の家族や被害者の家族を傷つけてしまうことが分かったと思います。
しかし、飲酒運転の代償はそれだけに留まらず、加害者の勤務先も責任を問われます。
では実際に飲酒運転が起こると、会社はどうなってしまうでしょうか。
第2回目は「西鉄グループ従業員から飲酒運転者が出た場合」を例に考えていきましょう。
会社(加害者勤務先)のその後
1.企業ブランドの失墜
※2013年アルコール検知不正発覚時の新聞記事
飲酒運転を起こすと、その事実がテレビや新聞で大々的に報道されます。
また、安全最優先を掲げる西鉄グループ従業員の事案では、会社名も含めて報じられ、
それがSNS等で拡散されると、世間から厳しい非難を受ける ことになります。
○お客様から西鉄グループに寄せられた実際の声(2013年)
・飲酒運転のニュースで信頼は全くない
・利用したくない気持ちで、CMすら嫌になる
・地元企業であるが、飲酒検知不正で信頼性なし
飲酒運転は、個人の犯罪として報じられるだけではありません。
「安全で安心できる西鉄グループ」から「危険で不安になる西鉄グループ」へと企業イメージは失墜し、
そのブランドを大きく毀損してしまいます。
2.お客様から選ばれなくなる

↑
西鉄ブランドの毀損は最終的に、西鉄グループ全体の業績悪化を招きます。
過去に発生した運輸部門の不祥事の影響は、他の部門にまで大きく影響しました。
あなたは飲酒運転を報じられるような会社の商品やサービスを、選びたいと思いますか?
地域とともに歩む企業だからこそ、お客様の信頼を失うようなことがあってはいけません。
3.行政処分を受ける

また、業務に関わる飲酒運転では行政処分により、会社の責任も問われます。
運輸事業を営む会社では、飲酒運転によって車両停止処分や事業許可取消処分が下されると
最悪の場合、バス・鉄道・タクシー・貨物の営業が一切できなくなる事態すら招きかねません。
飲酒運転は部門を問わず、絶対にやってはいけませんが、運輸部門は特に影響が大きいことを胸に刻んでおく必要があります。
飲酒運転者を会社から1人でも出してしまうと、西鉄グループ全体に大きな爪痕を残します。
西鉄グループでも過去にアルコールに関する不祥事を2回も起こしており、決して他人事ではありません。
過ちを繰り返さないためにも、各社・各部署で飲酒運転防止啓発ビデオ「記憶にとどめ、風化させない」を視聴して、どうしたら飲酒運転を防げるか考えてみましょう。
※「記憶にとどめ、風化させない」動画サイトはこちら!
→http://www2.nnr.co.jp/inshu/bokumetu_wmv01.htm



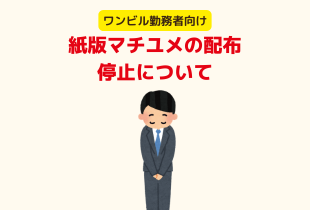








この記事へのコメントはありません。